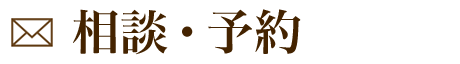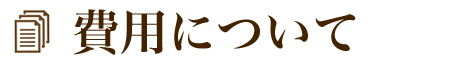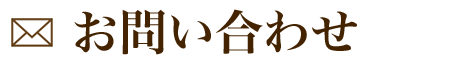武富士贈与税判決に見る恣意的課税への警鐘
(平成23年4月寄稿)
今年の2月、ある税務訴訟の判決が最高裁で言い渡されました。この判決は、国が逆転敗訴したことに加え、約2000億円という莫大な還付が見込まれることで世間の耳目を集めましたが、税務署による恣意的な法解釈に基づく課税に警鐘を鳴らすものとしても大きな意義があります。今回はこの判決を通して、租税法上の概念をいかに解釈すべきかという問題について指針を提供したいと思います。
住所の国外移転による贈与税の回避。
個人が資産の贈与を受けると、その者に贈与税が課されます。しかし、平成12年の法改正前においては、この贈与税の「抜け道」が指摘されていました。当時の相続税法では、贈与税が課されるのは、譲受人が国内に住所を有する場合か、贈与財産が国内にあった場合のいずれかと規定されていたため、譲受人の住所と贈与財産の双方を国外に移転させた上で贈与を実行すれば、贈与税は課されないこととなっていたのです。
この「抜け道」を実行したのが、消費者金融大手である武富士の創業者A夫妻とその長男Bです。A夫妻は、時価1000億円以上もの武富士の株式を有していたのですが、これをそのままBに贈与すれば、巨額の贈与税がBに課されてしまいます。そこで、① Bは3年半もの間、約3分の2の日数を香港に、約4分の1の日数を国内に滞在するという生活を送り、②A夫妻は、その期間中に武富士の株式を彼らが出資するオランダ法人に贈与し、その上で同法人の出資持分をBに贈与しました。これによりBは武富士の株式を間接的に取得したのです。
ところが、税務署はBに対し、Bが国内に住所を有していたとして上記出資持分贈与について贈与税等を課したことから、Bがこれを不服として訴訟を提起しました。
相続税法における「住所」の定義とは
この事件の争点は極めてシンプルです。すなわち、贈与時点でのBの住所はどこにあったか、という点です。一審は、Bが国外に住所を有していたとしてその請求を認容。これに対し控訴審は、Bは贈与税回避目的で出国したのだから滞在日数を重要視することは相当ではなく、国内に住所を有していたとして請求を棄却。
Bの上告を受けて最高裁は、Bの請求を認容した一審を支持する逆転判決を言い渡しました。判決理由を要約すると、①相続税法上の「住所」とは、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、民法上の「住所」と同意義に解釈すべきである。②「住所」であるか否かは、従来の判例のとおり、客観的に生活の本拠たる実体を備えている否かという観点から判断すべきである。③Bが約3分の2の日数を香港に滞在していたこと等からすれば、香港に住所を有していたというべきである。④Bが贈与税回避の目的を有していたとしても、客観的な生活の実体が消滅するものではない。というものです。
租税法上の概念の解釈のあり方
税務署は、Bが贈与税回避目的で出国したことを考慮すれば香港に「住所」を有していたといえないとして贈与税を課しました。しかし、「住所」については、民法が「生活の本拠」と定義し、従前の判例上「生活の本拠」の実体の有無は客観的に判断すべきとされています。相続税法の「住所」をこれと別の意義に解釈すべき根拠はありません。
租税法律主義とは、課税に法律の根拠を要求する原則ですが、課税庁により法律が恣意的に解釈されるとすれば、租税法律主義が有名無実なものとなってしまいます。AとBが行ったような租税回避行為の当否は別としても、課税庁が徴税確保を目的して相続税法の「住所」を恣意的に解釈することは許されないのです。
課税庁の法解釈は、とかく徴税に有利な方向に寄りがちですが、そのような解釈が常に正しいとは限りません。税務署の見解に疑問を覚えた方がいらっしゃれば、専門家にご相談することをおすすめいたします。